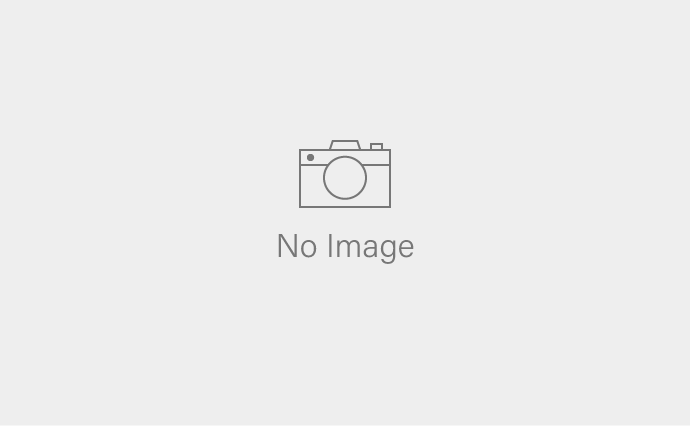JooLa Linus 中国式で出場した東京都スポーツ大会
JooLa Linus 中国式(廃版)に、表面Helfire-X、裏面木星超極薄0.7mmを貼って出場したのが2025年5月4日の東京都都民スポーツ大会でした。武蔵野市の代表チームの一員としての参加は初めてだったのですが、70代の私以外は東京都の上位や全国クラスの選手によるチームだったので、試合中のアドバイスがとにかく有難くて勉強になりました。1回戦、2回戦は接戦ながら勝ち、チームも勝って3回戦に進みました。頂いたアドバイスは、「一番いい技術を生かして戦うこと、その技術は高速プッシュだ」ということでした。もう一つは、「細かなフットワークを生かすとミスを減らせる」でした。3回戦は優勝した渋谷区のS藤選手に負けました。3ゲーム目こそ接戦ですごく盛り上がったのですが、最初はフォアに出される高速ロングサーブに対して当てることもままならない状態でした。そこで、「ラケットがもう少し大きければ」とか、「ラケットがもう少し柔らかければレシーブが台に収まったかもしれない」とか、技術の向上よりも「ラケットの最適化」に意識が行ってしまいました。
和の極み蒼中国式 で出場した八王子リーグ戦でプッシュを打たれた
「ラケットがもう少し柔らかければレシーブが台に収まったかもしれない」とか、「プッシュやスマッシュの安定性が良くなればもっと勝率が上がるかもしれない」という意識で、「メンバーが足りないので助っ人をやって欲しい」と言われて喜んで参加した、5月11日の八王子のリーグ戦でした。「助っ人だから負けるわけにはいかない」と思い、「和の極み蒼の表面にHelfire-X、裏面にUFO超極薄0.5mm」という鉄板の安定性をもったラケットで参加しました。ところが、です。年代別ではないので、若い選手も相手です。高速(と思った)プッシュや粒高スマッシュをことごとくカウンターされて惨敗してしまいました。「棄権防止の助っ人」以上の役割を果たせなくて、申し訳ないやら悔しいやら。「表面・裏面ラバー固定のラケット選択実験」を行うしかない、と決意しました。「方向が違っているんじゃない?」というツッコミが入りそうですが・・・。
MI青春卓球CLUBの高橋聖龍コーチのアドバイス付ラケット選択実験
八王子での惨敗の4日後、調布駅近くのMI青春卓球CLUBで、ワールドラバーマーケット(WRM)の動画で素晴らしいパフォーマンスを披露なさっているペン粒の高橋聖龍コーチと、私は向かい合っていました。6種類ほどラケットを持って行きましたが、主に比較したのは次の4種類でした。①JooLa Linus 中国式(廃版)、②Andro 和の極み蒼中国式、③Stiga Energy Wood(重め;91g)、④NEVAGIBAマジックウォール2です。どのラケットもWRMの動画では素晴らしい性能を発揮しています。どのラケットも素晴らしいのです。そう、使い手の技術レベルや強み、弱みに合っているかどうかがポイントなのです。「へん粒」の私に、「今の時点で合っているラケット」はどれかが問題なのです。さすがに、全く同じ超極薄ラバーを6枚用意することはできなかったので、裏面は木星超極薄0.7mmとUFO超極薄0.5mmが混在していました。

左:Andro 和の極み蒼中国式、右:JooLa Linus 中国式(廃版)

左:NEVAGIBAマジックウォール2、右:Stiga Energy Wood
大体の傾向は想像できていました。欲しい情報はただ一つ。プロコーチがどの程度カウンターしにくい粒スマッシュやプッシュが打てているかです。スマッシュに不安定さはあるものの、JooLa Linusのスマッシュやプッシュは「キレキレのボール」で、和の極み蒼の打球はカウンターされやすく、エナジーウッドはその中間という評価でした。マジックウォール2はプッシュで相手を押し込むというラケットではなさそうでした。JooLa Linusは薄い7枚合板ですが、硬いクルミ材の効果が出ていると考えました。いずれにしても、表(おもて)面がHelfire-XのOX(スポンジ無し)なら、ラケットは固い方がよさそうです。スマッシュの不安定さは練習による技術の向上で何とかすれば良い?
上の結論で廃版のJooLa Linus 中国式を使い続けるという結論になるのであれば普通なのですが、そこは「へん粒」です。違うことを考えました。何を考えたか?次回のお楽しみです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b97d113.aa257b3a.4b97d114.6c436388/?me_id=1322035&item_id=10000643&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftransports2nd%2Fcabinet%2Fwrm%2Fxwrm-bom-003n-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)